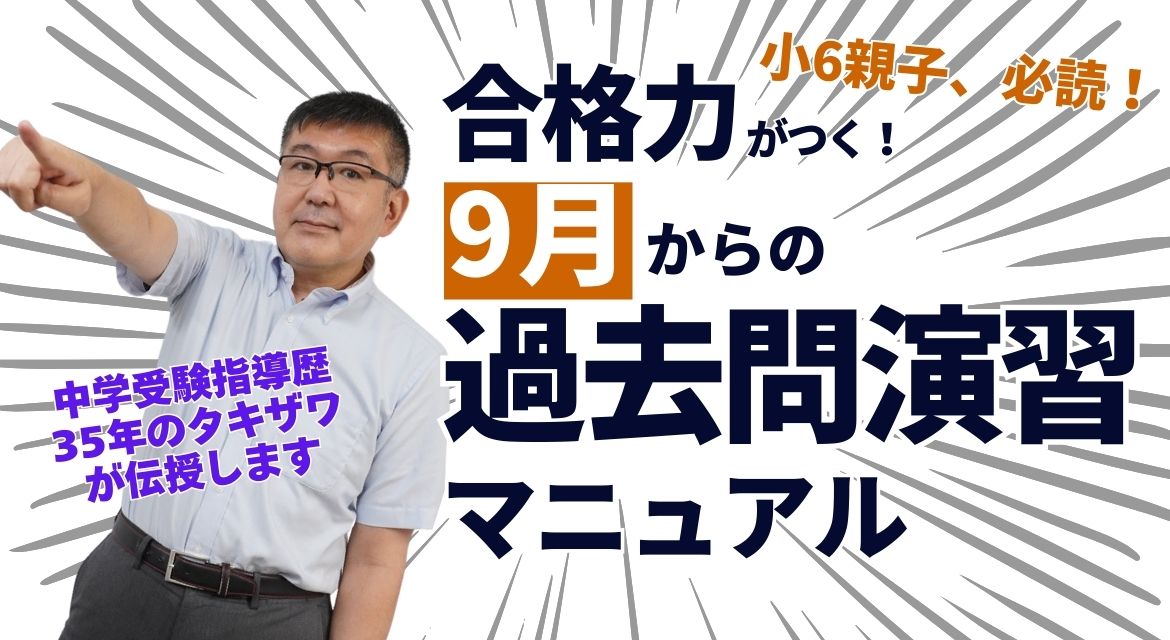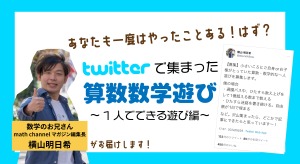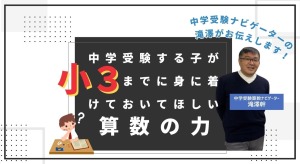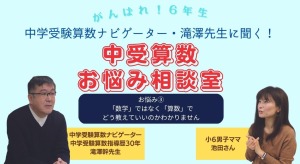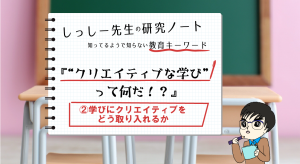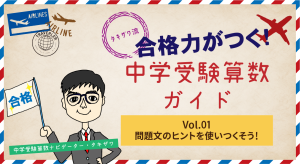こんにちは、中学受験算数ナビゲーターの滝澤です。
中学入試に挑戦する受験生のみなさんは、この夏、今まで学習してきた内容の総復習と自らの弱点克服のために一生懸命頑張ってきたことと思います。何よりも健康には気をつけて、悔いなく頑張ってください。
さて、夏が終わると多くの受験生は志望校の過去問演習をするのではないでしょうか。
今回は、中学受験指導歴35年の私が考える、算数の過去問演習の意義と実践について、小6生と保護者の方にお伝えしたいことを書いていきたいと思います。

過去問演習とは
過去問演習とは、志望校で出題された入学試験を本番のように時間をはかり、指定の解答用紙に解くことをいいます。何問か抜粋して練習することではありません。
その年の試験に出題されたすべての問題を試験時間すべて使って解くことに意味があります。普通の問題演習と何が違うのか、まずはここからお伝えしたいと思います。

過去問演習をやるのは「試験慣れ」のため
「試験慣れ」という言葉があります。多くは問題を解く順番や時間管理についていうことが多いと思います。
試験で高得点を取るために最も重要なことは、解くべき問題を取捨選択して、正解すべき問題ではミスをしないことです。ミスをしないためには、ていねいに問題を解くことが大切です。
そのためにはある程度ゆっくり読んでゆっくり書く必要があります。
しかし試験時間は決まっていますから、時間配分をしっかり考えなければなりません。
そのためには、正答率の低そうな問題は後回しにするなどの問題を解く順番の工夫も大事ですね。
実際の試験で緊張してしまったりすると、わかっているつもりでも、この時間管理と問題の優先順位、取捨選択ができないことが多いのです。
多くの中学校では出題形式は例年同じことが多いですから、問題量や難易度に慣れていると、作戦通り問題を解くことができやすくなります。
学校ごとの出題傾向と自分との相性
出題傾向を熟知しておくことも過去問演習の1つの目的です。
過去問演習をした上で、よく出題されるのに苦手な問題があれば、集中して練習することができますね。
あまり出題されない問題をたくさん練習する必要はありませんが、本当に行きたい学校であれば、そこでよく出題される問題は得意になっておきたいですね。
このように、過去問演習は自分がどの単元を集中して学習すべきかを教えてくれます。ここを第一に考えるのであれば、点数はあまり気にする必要はありません。
過去問演習の手順
ただ時間を計って過去問を解きなさいと言われると、いつもの問題演習のように解いてしまう子供も大勢います。しかし、いつも通り解いてしまうのはもったいないと思います。
自分の志望校の過去問を解くのは特別なことです。しっかり手順も確認しておきましょう。
過去問演習の手順
- 問題も解答用紙もコピーして解く
問題も解答用紙もコピーして、解くようにしましょう。過去問集の冊子に直接書き込んでしまうと、解きなおしがやりにくくなってしまいます。 - 試験時間は厳守して解く
試験時間は厳守して解くようにしましょう。早く終わったら見直しをすることも練習です、時間が足りないからといって、時間を延ばすこともやめましょう。得点を記録しておきましょう。 - 緊張した状態を作ってから問題を解く
これは本番の試験なんだと自ら思い込んで、少し緊張した状態を作ってから問題を解くようにしましょう。リラックスした状態で過去問演習をしても効果は半減です。

全部の問題を解きなおす必要はありません。
試験には正答率の低い問題が必ず出題されていると思って構いません。
合格ライン以上の点数が取れているのであれば、そのような問題は解きなおしをする必要はありません。
でもどの問題が正答率の低い問題かはわからないという方もいらっしゃるかもしれません。その場合は、解説をまず読んでみることをおすすめします。
解説を読んでも意味がわからない場合は解きなおす必要はありません。
一番よく聞かれる質問は、「何年分やればいい?」
「何年分やればいいの?」
これはよく聞かれることです。この答えは、過去問演習をやるのが楽しいと思えるかどうかによって変わってきます。
すなわち何年分やりたいか?なのです。
自分が行きたい学校の過去問があったらあるだけ解きたいという子どももいるでしょう。とても自然な気持ちだと思います。
学校によっては30年分以上の算数の過去問が市販されている中学もあります。それはやらなければならないのではなく、やりたいから需要があるのです。
合格ラインを超える点数が取れるのであれば直近の3年分もやれば十分かと思いますし、あまり点数が取れないのであれば、気が済むまでやるべきかと思います。
過去問演習は、「モチベーションアップのため」にやる。
子どもにとって、同じ算数の問題を解くのであれば、ただ問題演習をするよりも、自分が実際に受験する学校の過去問を解く方がやる気がでます。
もし、自分が受験するのに解きたくないと思ってしまうのであれば、もう一度受験する意味を考え直した方がよいかもしれません。

合否予想をするための過去問演習はNG
ただし、過去問演習の点数だけをもとに合格か不合格かを予想しようとすることはおすすめしません。
多い方だと4~5校の過去問演習をしなければならないので、必然的に9月、10月から始めることになってしまいます。しかし、受験生の実力が最も伸びるのは12月~1月です。
つまり、初めは合格ラインを超えることは稀なのです。この点数を元に「こんな点数だと合格できないよ」などとプレッシャーをかけることは、「モチベーションアップ」とは真逆の方法になってしまいます。
過去問演習の1周目は自分が苦手としていることをしっかり見極めることこそが最も大切だと考えましょう。2周目、3周目で合格ラインを超えればよいのです。
自分を信じることが大切です
過去問演習でどんな得点であろうとも、直前までは焦る必要はありません。あきらめずにわかったフリをせずに問題を解き続ければ必ず合格できる力はつきます。
他人と過去は変えられないけれども、自分と未来は変えられます。
過去問演習を通して強く成長していく子どもたちを応援しつづけましょう。

(文責:滝澤幹)
『線と四角と表でわかる つるかめ算』(日東書院本社)発売中!
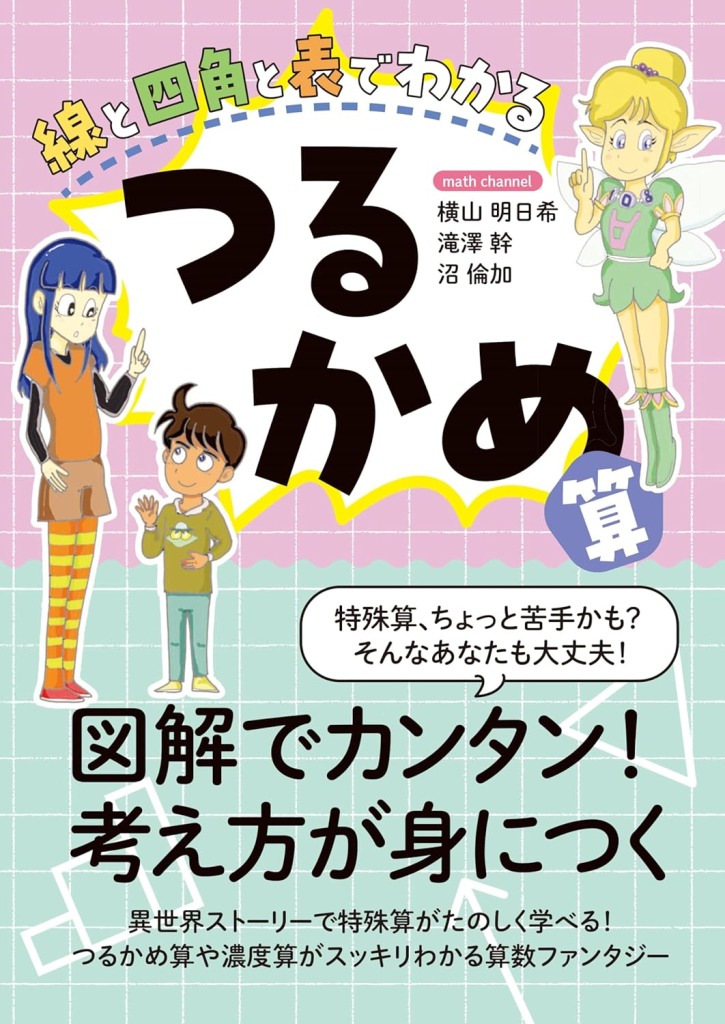
「つるかめ算」「和差算」「濃度算」「旅人算」などの特殊算を図解で解説している本『線と四角と表でわかる つるかめ算』(日東書院本社)が発売中です!
著者プロフィール

タッキー先生(滝澤 幹 たきざわ かん)
中学受験算数ナビゲーター
御三家筑駒中学受験専門塾にて指導歴30年。「算数の楽しさは正解だけではない」「すべての小学生に算数の難問を解く楽しさを知ってほしい」と思い、math channnelに参加。算数表現力ゼミを主催。共著書に『親子で楽しむ!中学受験算数』(平凡社刊)がある。